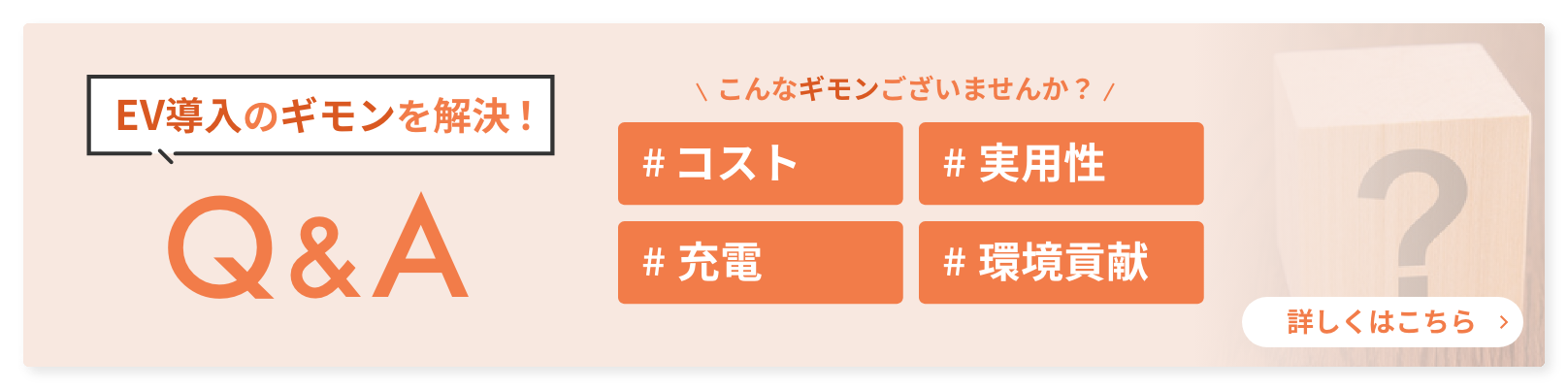EV(電気自動車)の車検はガソリン車とどう違う?費用も解説

EVはガソリン車と同様に車検を受ける必要がありますが、検査項目や費用などに違いがあるのか気になる方も多いのではないでしょうか。EVはガソリン車よりも検査項目が少なく費用も安い傾向がありますが、車両の状態や車検を受ける場所などによって多少の違いがあります。
本記事では、EVとガソリン車の車検の違いや費用、EVの車検を受けられる場所などを解説します。
EVの車検内容
EVはガソリン車と自動車と同様に、公道を走行する以上は車検を受けなければなりません。
以下では、EVとガソリン車の車検の違いを解説します。
ガソリン車の車検との違い
EVはガソリン車とは車体の構造が異なるため、車検の内容や費用も異なります。
EVは消耗品・部品の点数がガソリン車よりも少ない分、交換すべき部品や検査項目が少ない点が大きな違いです。また、費用も比較的安価で済みます。
例えばEVにはエンジンがないため、以下のようなガソリン車特有の部品やシステムの点検・整備が不要です。
【エンジン関連】
・エンジンオイル、オイルフィルター
・点火プラグ
・エアフィルター
・タイミングベルト
・冷却水(エンジン用) など
なお、エンジンオイルの点検・交換は不要ですが、ブレーキオイルや減速機のオイルは点検対象となります。
【排気系統】
・マフラー
・排気ガス浄化装置 など
【燃料系統】
・燃料フィルター
・燃料ポンプ など
一方で、EVにはガソリン車にないシステムが搭載されているため、以下の項目が車検に含まれることがあります。
・バッテリー(劣化具合や容量の確認、冷却システムの点検)
・モーター(動作確認や異音の有無)
・充電ポート(接続部の摩耗や異常の有無、防水性や接触不良の確認)
・インバーターやコンバーター(電力変換装置の動作確認) など
また、ガソリン車とEVに共通するブレーキ系統やタイヤ、ステアリング、ライト、ワイパー・ウォッシャー液、車体損傷や錆の有無なども点検項目に含まれます。
EVの車検を受けるタイミング
EVの車検を受けるタイミングは、ガソリン車と同様に新車購入から3年後、それ以降は2年ごとです。
車検の実施は法律で定められているため、決められたタイミングで車検を受けないと安全上の問題が生じやすくなるだけでなく、罰則・罰金の対象にもなります。
また、車検のときだけ点検を行えばよいわけではなく、所有者は1年に一度の「定期点検整備」を行うことが義務付けられています。
ただし、EVはガソリン車に比べ部品の点数が少ないため、日常の点検・整備の負担は少ない傾向があります。
EVの車検を受ける場所
EVの車検を受けられる場所には、大きく分けてディーラーと整備工場があります。
ディーラー
ディーラーは自動車メーカー直営の販売店、またはメーカーと特約店契約を結んでいる正規の販売店のことです。
対象のメーカーの販売に特化しているため、特定の車種に精通した整備スタッフが在籍していることが一般的です。EVを販売しているディーラーであれば、ほとんどの場合EVの車検にも対応しており、充実した整備機器でEVの点検・整備を受けられます。
バッテリーの劣化具合を詳細に点検してもらいたい場合には、メーカー直営のディーラーに依頼するのがおすすめです。
ただし、高品質なサービスを提供してくれる半面、費用は比較的高い傾向があります。
整備工場
民間の整備工場でもEVの車検を受けることができます。
整備工場は「認証工場」と「指定工場」に分けられます。
・認証工場
車の分解整備を行える工場のうち、地方運輸局の認証を受けた工場のことです。車検場への持ち込みが必要となるため、車検が完了するまでに2〜3日程度かかることが一般的です。
・指定工場
認証工場のうち、さらに一定の条件を満たした工場を指します。車が保安基準をクリアしているかを工場内で確認でき、車検場への持ち込みが不要である点が特徴です。そのため、数時間〜1日程度で車検を終えられます。
費用相場としては、ディーラーよりも整備工場の方が比較的安い傾向があります。
ただし、ディーラー以外の整備工場の場合、工場によってはEVの車検に対応できない場合があります。
EVに特化した点検項目や安全に関する知識が必要なため、EVの整備に対応している工場であるか確認しておくことが重要です。
EVの車検費用
EVの車検費用には法定費用と基本費用があります。
法定費用
法定費用は、車検時に支払う必要がある税金、保険料、印紙代を合わせた費用のことです。金額は全国一律で決まっています。
具体的には以下の費用が含まれます。
・自動車重量税:
新車購入時と車検時に、重量や車種、新車登録時からの年数に応じて課される税金です。EVは新車時と初回車検時の2回分が免除されるため、一般的な乗用車クラスで数万円程度費用を抑えられます。
・自賠責保険料:
自動車の運転により人身事故を起こした場合に備えるための保険です。法律で加入が義務付けられており、保険料はガソリン車とEVで大きな差異はありません。
・印紙代:
国に収める検査手数料を支払うための印紙・証紙の料金のことです。
車検場所や車種によって数百円の差が生じますが、ガソリン車とEVで大きな違いはありません。
基本費用
基本費用は車検を行う業者に支払う料金のことです。「車検基本料金」に部品交換代や作業工賃など諸費用が上乗せされます。
依頼先の業者や利用者の乗り方によって料金は変わりますが、前述の通りEVは検査項目が少ない分、整備費用はガソリン車に比べると安くなる傾向があります。
ただし、タイヤの摩耗が激しく交換が必要な場合や、モーターに問題がある場合などはその分の費用が上乗せされます。
車検基本料金の相場としては、中型乗用車の場合ディーラーで4万円~、整備工場では3万円~が一般的です。
EVの車検はガソリン車よりもお得
EVもガソリン車と同じ頻度で車検が必要であり、法定費用と基本費用を合わせた金額を支払う必要があります。
ですが、部品の点数が少なく自動車重量税が免税される分、ガソリン車よりは費用を抑えられる場合が多いため、社用車/公用車のコスト抑制を考えているのであればEVを導入するのがおすすめです。
社用車/公用車のEV化を進める際には、車検費用だけでなく電気代が気になる方も多いかもしれません。電気代を抑えるには、EVとあわせてスマート充電の仕組みを導入すると良いでしょう。
EnneEV(エネーブ)は、EV充電インフラの導入とEV充電器の遠隔制御により電気料金の上昇を抑制するEVスマート充電サービスです。電気の使用パターンや会社設備の規模にあった最適なEV導入計画を提案し、EV充電器の遠隔制御により電気料金の上昇を抑制できます。
以下の資料では、「EVのコストは高い?」、「維持費はどう?」などのよくある疑問に回答しています。ご関心のある方はぜひご覧ください。
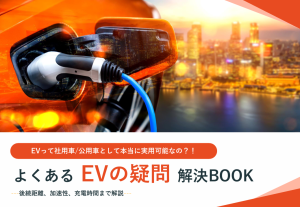
よくあるEVの疑問解決BOOK
本資料では、航続距離、加速性、充電時間などEVのよくある疑問に回答しています。EVについて知りたい方はぜひご覧ください。