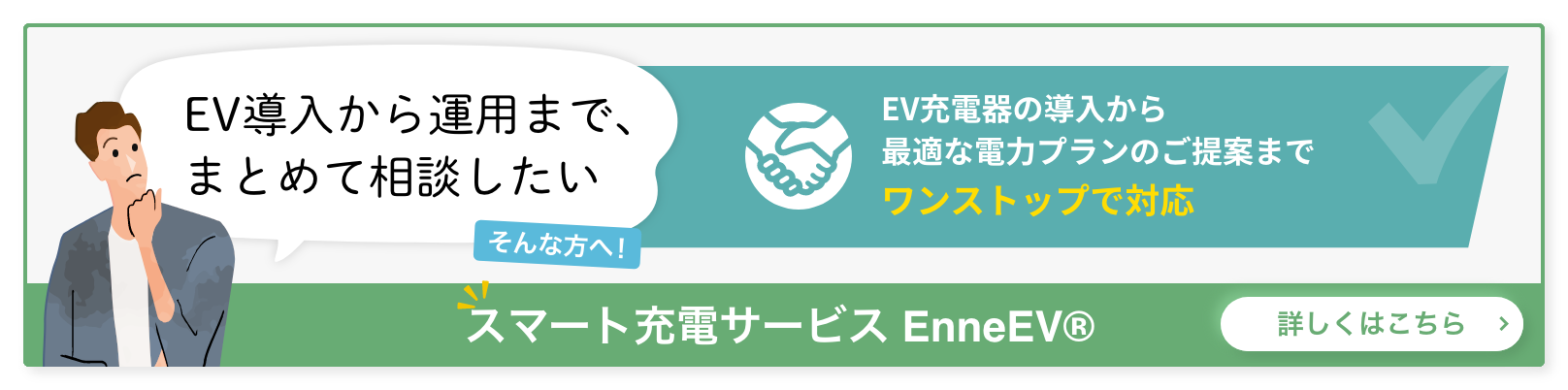【2025年最新】EVの普及率は?
日本と世界の取り組みも解説

脱炭素をはじめ、環境対策が世界的な課題となる中、世界的にEVの存在感が増しています。日本でもEVは徐々に普及していますが、世界に比べるとまだ普及の途上といえる状況です。
本記事では、日本と世界のEV普及率やEVの普及に向けた取り組みを解説します。
目次
日本のEV普及率
日本自動車販売協会連合会※1によると、2024年の普通乗用車市場におけるEVの普及率(新規登録台数)は1.35%(約34,000台)です。
2021年は0.88%(約21,000台)、2022年は1.42%(約32,000台)となっており、2023年には1.66%(約44,000台)で推移しています。
| 普及率 | 新規登録台数 | |
|---|---|---|
| 2021年 | 0.88% | 約21,000台 |
| 2022年 | 1.42% | 約32,000台 |
| 2023年 | 1.66% | 約44,000台 |
| 2024年 | 1.35% | 約34,000台 |
軽自動車市場に関しては、全国軽自動車協会連合会※2のデータによると、2024年度のEV販売台数(日産「サクラ」と三菱「ekクロスEV」および三菱「Minicab MiEV」の合計)の全体に占める割合(普及率)は2.2%です。
2023年度の普及率は3.2%であり、普通乗用車、軽自動車ともに2024年に入り普及が停滞気味になっています。
出典:
※1日本自動車販売協会連合会
※2全国軽自動車協会連合会
世界のEV普及率
では、日本と比較して海外のEV(プラグインハイブリッド車(PHEV)を含む)普及率(販売比率)はどうなっているのでしょうか。
以下では、EVの大きな市場であるアメリカ、ヨーロッパ、中国の事例をご紹介します。
アメリカのEV普及率
IEA(国際エネルギー機関)の統計によると、2024年のアメリカにおけるEVの普及率は、新車販売台数の約10%(約152万台)に達しました。2023年の約9%から微増しています。
テスラを中心に自動車メーカーがさまざまなEVの車種を投入しており、2024年までに少なくとも9つのEVモデルが提供されています。
日本に比べるとEV普及率は高いですが、後述のヨーロッパや中国に比べると停滞している状況です。
出典:IEA
ヨーロッパのEV普及率
2024年の欧州連合(EU)のEVの普及率は約21%(新車販売台数は約227万台)であり、前年の約22%から減少しています。
ヨーロッパの主要国の動向は以下の通りです。
・ドイツ:
政府のEV購入補助金が2023年末に終了した影響で、2024年のEV販売台数は前年から約13万台減少し、57万台でした。普及率も24%(2023年)から19%(2024年)に低下しています。
・フランス:
2024年のEV販売台数は前年から約2万台減の約45万台、普及率は1%減の約24%となっています。
・英国:
2024年のEV販売台数は前年から約10万台増の約55万台であり、ヨーロッパでドイツに次ぐ大きさのEV市場となりました。普及率は4%増の約28%となっています。
・スウェーデン:
2024年のEV販売台数は、前年から約1万4,000台減の約15万7,000台でした。普及率も2%低下し約58%となりましたが、依然としてEU域内で高い普及率を維持しています。
・ノルウェー:
2024年のEV販売台数は、前年から約3,500台増の約11万3,500台でした。普及率は2%増の約92%であり、ヨーロッパで最も高い水準を誇っています。
出典:IEA
中国のEV普及率
中国の2024年のEVの市場シェアは、前年に比べ10%増の約48%です。販売台数は前年(2023年)に比べ約320万台増の約1,130万台であり、世界最大のEV市場となっています。
2020年にはEVのシェアが5.7%だったことを踏まえると、ここ数年でEV市場が急拡大していることがわかります。
EV普及に向けた各国の目標と取り組み
本章では、EV普及に向けた日本と世界(ヨーロッパ、中国)の目標と取り組みについて解説します。
日本の目標と取り組み
日本政府は、2035年までに新車販売をすべて電動車(EV、PHEV、HEV、FCV)にする目標を掲げ、2030年時点ではEV・PHV:20~30%、FCV:~3%、HEV:30~40%を目指すこととしています。
また、2050年までにカーボンニュートラルを達成することを掲げており、自動車部門はその中核に位置づけられています。
こうした目標を実現するため、政府は「グリーン成長戦略」にて「自動車・蓄電池産業における電気自動車の普及加速」を明言しました。2023年には「充電インフラ整備促進に向けた指針」を示し、2030年までに30万口の充電器設置を目指しています。
EVの普及に向けた日本の取り組みや課題については、以下の記事で詳しく解説しています。

ヨーロッパの目標と取り組み
ヨーロッパでは、2050年カーボンニュートラルの実現や、2035年以降「e-fuel」(二酸化炭素と水素を合成した液体燃料)を使用する車両以外のガソリン車の販売を禁止する目標を掲げています※1。
※1:JETRO「EU、乗用車・バンのCO2排出基準の新規則施行へ、電動化方針に変わりなし」
主な取り組みとしては、CO₂排出量55%削減(1990年比)を目標に、EV普及を中核施策として掲げる「Fit for 55」政策パッケージの実施※2のほか、高速道路上に60kmごとに急速充電器を設置する充電インフラの義務化※3を進めています。
※2:JETRO「EU、2030年までのGHG排出55%削減に向けたFit for 55関連法案がほぼ成立」
※3:IEA「Outlook for electric vehicle charging infrastructure」
また、EV購入補助金をはじめ各国で独自の補助政策も展開しています。ただし、ドイツやフランスでは補助金制度の終了や条件の厳格化などが行われており、今後もこれまでと同様にEVが普及するかは見通せない状況です。
中国の目標と取り組み
中国では2060年カーボンニュートラルの達成や、2035年までに新車販売のほぼすべてをNEV(新エネルギー車)にする目標※4を掲げています。
※4経済産業省「自動車分野のカーボンニュートラルに向けた国内外の動向等について」
具体的な施策として、NEV産業育成計画による自動車メーカーへのNEV販売比率の義務化や、EV購入者に対する補助金や購入税の免除、政府主導の充電インフラの拡充など、さまざまな政策を展開しています※5。特に充電インフラの整備に力を入れており、中国国内のSAの約90%で充電施設が設置されている状況です※6。
さらにEV関連技術の研究開発を支援し、バッテリー技術やリサイクル技術の向上を目指しています。
※5:CSIS「The Chinese EV Dilemma: Subsidized Yet Striking」
※6:中華人民共和国中央人民政府「国内の高速道路サービスエリアのほぼ90%が電気自動車充電施設を建設しています」(タイトルは日本語に翻訳)
まとめ
脱炭素社会の実現に向けた取り組みが世界的に加速する中、欧州や中国といった世界の主要国は明確な数値目標を掲げながらEVの普及に努めています。
特に中国は、市場規模・政策支援・インフラ整備のいずれにおいても先行しており、世界のEV市場を牽引しています。
一方、日本は他国と比較してEVの普及ペースがやや緩やかであり、充電インフラの拡充を通じて普及を後押ししている状況です。
こうした中でEVを導入するためには、コストを抑えながら効率的に自宅や会社で充電できる仕組みを構築することが重要です。
エネットでは、EVの導入を支援するサービスとしてEnneEV®(エネーブ)を提供しています。EnneEV®(エネーブ)は、EV充電インフラの導入とEV充電器の遠隔制御により電気料金の上昇を抑制するEVスマート充電サービスです。
企業のEVシフト、EV充電器導入の相談から、設備機器の準備、設置工事、アフターケアまでワンストップで対応可能です。充電制御により電気代を契約電力内にコントロールすることで、コストを抑えながらEV充電器を導入できます。
以下の資料では、EVシフトの現状や社用車EV化のメリット、EV導入の際のステップなどを解説していますので、ご関心のある方はぜひご覧ください。

社用車EV導入 ガイドブック
本資料では、世界と日本のEVシフトの現状やEV導入の際に考慮すべきポイントをわかりやすくご紹介しています。社用車としてのEV導入をご検討されている企業のご担当者様はぜひご覧ください。